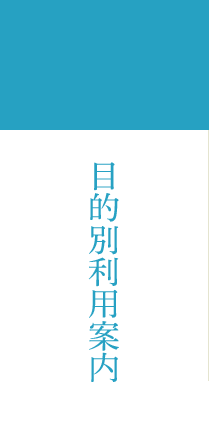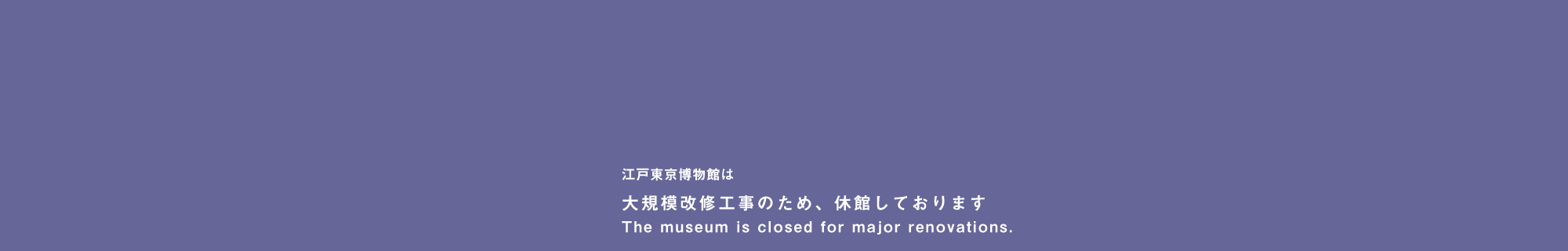
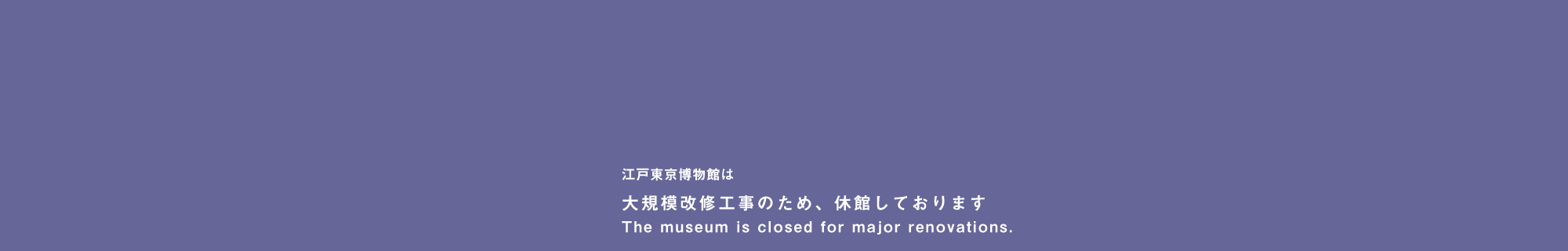
江戸東京博物館図書室のレファレンス事例集
国立国会図書館運営レファレンス協同データベース![]() で江戸東京博物館図書室が提供した事例が検索できます。
で江戸東京博物館図書室が提供した事例が検索できます。
(※「レファレンス」とは利用者が学習・研究・調査等で図書室に情報を求めた場合に、図書室の機能を活用して、参考となる資料をご案内するサービスです。)
●フリーワードから探す
事例をフリーワードから検索できます。
●江戸東京博物館図書室の事例をすべて見る
2016/02/03
東京都港区六本木の地名は「××木」という武士が六人住んでいたからというのは本当か。(2015年)
(回答) 参考資料によると、一般的に諸説伝えられる古い地名の由来は、どの説が正しいと断定するのは難しいといえます。この場合も(1)「木」と付く名前の武家屋敷があった(2)大木が六本あった(3)江戸六方の男達(おとこだて)が住んでいた等の説があります。詳しくは回答プロセスと参考資料をご参照ください。 (回答プ...
詳細を見る
2015/12/15
幕末から明治時代の写真で、手を隠して写っている人物が多く見られるが、 それは何故か。(2015年)
『写された幕末 石黒敬七コレクション』【資料1】に、「手が大きくなると迷信され、揃って手を袖のなかに隠す武士と遊所の女達。」とあります。『歴史読本 2014年5月号 古写真集成 幕末・明治の100人』【資料 2】にも、写真に写ると手が大きくなる、また、手によくないことが起こるという俗信があったという説が載って...
詳細を見る
2015/09/24
常設展示室にある両国橋の模型の図面はあるか。(2015年)
(回答) 模型は現存するいくつかの史料を参考にしており、図面は館蔵図書としてはありません。詳しくは回答プロセスと参考資料をご参照ください。 (回答プロセス) 【資料1】『復原・江戸の町』に模型作製時に使用した参考史料名が記載されている。それによると、「図面は、安永9年(1780)と明治元年(1868)の二種類...
詳細を見る
2015/09/24
『仮名手本忠臣蔵』の赤穂義士たちはなぜ揃いの火事装束を着ているのか。実際はどうだったのか。(2015年)
(回答) 参考資料によると、実際の討ち入りでは火事装束を揃えたのではなく、黒い小袖を身に着けるよう申し合わせ、各自で装備したと思われます。(備考※1,2に堀部安兵衛の着用したとする装束画像あり。) 『仮名手本忠臣蔵』における火事衣裳については、実際に着用した黒い小袖が火事装束に似ていたので舞台用に派手...
詳細を見る
2015/08/19
長火鉢の「猫板」はネコが居眠りすることから名付けられたのか。 (2015年)
明確な由来は不明ですが、寒がりな猫が乗っても不自然ではない部分ということから、猫と関連付ける文献が見られます。詳しくは回答プロセスと参考資料をご参照ください。 (回答プロセス) 【資料1】『日本国語大辞典』第15巻 によれば、「ここによく猫がうずくまるのでいう」。【資料2】『大江戸復元図鑑 庶民編』...
詳細を見る
2015/08/19
『東海道五十三次』を描いた江戸時代の浮世絵師、「歌川広重」と「安藤広重」はどちらが正しい呼び名なのか。(2015年)
(回答) 参考資料によると、かつては本姓の「安藤」と画号の「広重」を併用した「安藤広重」と表記されることがありましたが、現在は「歌川広重」と表記されることが多いようです。詳しくは回答プロセスと参考資料をご参照ください。 (回答プロセス) 【資料1】『もっと知りたい歌川広重 生涯と作品』によると「少々...
詳細を見る
2015/08/19
江戸時代の飲食店には「御品書き」と書かれたメニュー表があったのか。(2015年)
「御品書き」と書かれた参考資料は当館蔵書では見つけられませんでした。「覚」と書いてある資料もありますが、頭書きのない場合もあり、さまざまなようです。詳しくは回答プロセスと参考資料をご参照ください。 (回答プロセス) 【【資料1】『江戸あきない図譜』によると、「行灯に書かれた品書き」として「覚」と記さ...
詳細を見る
2015/06/08
鹿鳴館の図面は残っているのか。(2014年)
参考資料によると、設計者のジョサイア・コンドルが書いた図面は現在行方不明となっており、現在私たちが見られるのは推定図と、竣工後書かれた略図となっています。詳しくは回答プロセスと参考資料をご参照ください。 (回答プロセス) 【資料1】『復元鹿鳴館・ニコライ堂・第一国立銀行 江戸東京博物館常設展示東京ゾ...
詳細を見る
2015/06/08
江戸時代の「江戸三大名鐘」とはどれを指すのか。(2014年)
参考資料によると、江戸時代に「江戸三大名鐘」と呼ばれていたかは不明です。江戸の代表的な鐘として寛永寺、増上寺、浅草寺、天龍寺、市ヶ谷八幡宮等の鐘が紹介されていますが、「三大鐘」として紹介する文献も鐘の組み合わせがそれぞれ異なります。詳しくは回答プロセスと参考資料をご参照ください。 (回答プロセス)...
詳細を見る
2015/06/08
太田道灌の「山吹の里」伝説の地は都内のどこなのか。(2014年)
(回答) 参考資料によると、現在「山吹の里」伝説に関する史跡は都内に複数あります。荒川区荒川7-17-2(泊船軒内に史跡)、 豊島区高田1-10-5(山吹の里公園に由来板)、豊島区高田1-18-1(面影橋附近に史跡)、新宿区新宿6-21-11(大聖院内に山吹の里伝説の娘の墓)、新宿区西新宿2-11(新宿中央公園に太田道灌久遠...
詳細を見る
2015/06/08
正月遊びの定番、福笑いの起源は江戸時代か。(2014年)
所蔵参考資料によると、明確な年代は不明ですが、江戸中~後期頃には福笑いの原型といえるものが存在したと考えられます。正月の遊びとして定着したのは明治以降のようです。詳しくは参考資料をご参照ください。 (回答プロセス) 【資料1】『童遊文化史 考現に基づく考証的研究 第4巻』【資料2】『おもちゃ博物館 6 双...
詳細を見る
2015/06/08
八百屋お七の墓は現在東京に残っているか。(2014年)
参考資料によると、八百屋お七の墓は都内では円乗寺(住所:東京都文京区白山1-34-6)にあります。東京以外では、千葉県八千代市の長妙寺、岡山県御津町にもお七の墓と呼ばれている墓があります。 (参考資料) 【資料1】『都史紀要 39 レファレンスの杜-江戸東京歴史問答』東京都公文書館編 東京都公文書館 2003年...
詳細を見る
2015/06/08
7月7日七夕はそうめんの日と聞いたが、その由来は? この日、江戸でそうめんを食べる慣習はあったか?(2014年)
全国乾麺協同組合連合会のホームページによると、同連合会では昭和57年(1982)から7月7日七夕を「そうめんの日」と決めているとある。 そうめんは漢字で「素麺」あるいは「索麺」(索餅が原型)と書くが、『年中行事大辞典』には“『年中行事抄』は中国の故事を引きつつ、七夕に索餅を食せば瘧病にかからないと述べる”...
詳細を見る
2015/06/08
かつて東京都港区虎の門付近に「どんどん」と呼ばれていた滝があったようだが本当か。(2013年)
広重の連作である「名所江戸百景」の中の1点「虎の門あふひ坂」に描かれている滝のことではないかと思われます。 (回答プロセス) この作品は【資料1】『浮世絵大系 17 名所江戸百景 2広重画 』【資料2】『広重名所江戸百景』などに掲載されているものを当図書室にてご覧いただけます。 葵坂(あふひ坂)とは【資料...
詳細を見る
2015/06/08
大名行列において、大名がトイレに行きたくなったときどうしていたのか? "おまる"を乗せた駕籠(通称:おまる駕籠・厠駕籠)があり、大名は移動中に自分の駕籠からおまる駕籠に飛び移り済ませていたというのは本当か?(加賀前田藩での事例としてインターネット上で記載されている) また、組み立て式(携帯用)トイレの図版はあるか?(2013年)
資料により諸説あるようだが、“おまる駕籠・厠駕籠”といったものや、移動中に駕籠から駕籠へ飛び移ったという内容は当館所蔵の資料では確認できなかった。同様に図版も確認できず。 (回答プロセス) 【資料1】『江戸参府旅行日記 東洋文庫303』ケンペル著 斎藤信訳 平凡社 1977年 2910/170/77 (P18) 2・3...
詳細を見る
2015/06/08
ヤミ市の物価が出ている本はあるか。(2013年)
【資料1】『かたりべ 豊島区立郷土資料館だより 74』にはヤミ値と基準価格の比較一覧表があります。 webサイトでも見られます。 https://www.city.toshima.lg.jp/129/bunka/bunka/shiryokan/kankobutu/kataribe/documents/kataribe74.pdf (2015/7/20確認) (回答プロセス) 【資料2】『東京都江戸東京博物館調査報...
詳細を見る
2015/06/08
展示室に復元されている日本橋(備考※1参照)の中央にある少し高くなった板の名称と役割は?(2013年)
【資料1】『東京都江戸東京博物館調査報告書 第16集 日本橋 平成13年度シンポジウム報告』によると「中布板と言います。ここで半分ずつ接いで、左右に水勾配を付けている」と書かれています。また【資料2】『東京人』(no.243,第22巻第9号(2007.8))には、「橋の中央には、センターラインのように中布板が取り付けられ、...
詳細を見る
2015/06/08
江戸三座(市村座・中村座・森田座)の座紋を知りたい。(2013年)
【資料1】『歌舞伎事典 新版』によると、市村座:隅切角に鶴の丸→丸に橘(元禄3(1690)年)、中村座:舞鶴→隅切角に銀杏、森(守)田座:丸にかたばみ。 (回答プロセス) 市村座と中村座の座紋が変更された理由としては、【資料2】『江戸歌舞伎図鑑 芝居で見る江戸時代』によると、徳川家に鶴姫が誕生したので、鶴を...
詳細を見る
2015/06/08
江戸城の櫓(やぐら)は現在も残っているか。(2013年)
下参考資料によると本丸の富士見櫓、西の丸の伏見櫓、三の丸の巽櫓(辰巳櫓・桜田櫓)が残っている。 (参考資料) 【資料1】『天守再現!これが江戸城だ! 別冊宝島Study 1758』三浦正幸監修 宝島社 2011年 5218/217/0011-S00 (p.72-3) 【資料2】『皇居 自然・歴史・建築・行事…都心の杜を細見』JTBパブリッシング ...
詳細を見る
2015/06/08
江戸時代の枝豆は枝付きか。(2013年)
【資料1】『守貞謾稿』によると「江戸は豆の枝を去ず売る故に枝豆という。京坂は枝を除き皮を去ず売る故にさやまめという」と書かれています。(備考※1参照) (回答プロセス) 【資料2】『彩色江戸物売図絵』に枝豆売りの説明と絵がある。【資料3】『江戸川柳飲食事典』によると「十分に熟していない大豆を枝につけ...
詳細を見る